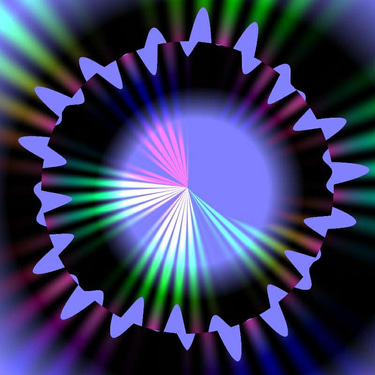危ないところだった』ロバート・フラー著
おい、次に鏡をじっと見つめすぎる前に、俺がいつも言ってることを思い出せ。もう忘れたようだな。ささやきについて話したんだ。君が記憶の中を後ろ向きに歩いていた時だ。人けのない浜辺で、忘れ去られた場所で、独りでか、あるいは自らの視線から呼び起こした想像上の伴侶と共に。君が自分の姿にすっかり魅了されていたからかと思った。だから実際は、君が自分自身と歩みながら、時折口にする罵声をもう一人の自分がたまたま耳にしたのかもしれない。少なくとも、あの清らかな浜辺が越えられない岩壁に変わるまではね。
覚えているだろう、岩が現れた途端、君はささやきを思い出していた。遅すぎたけれど。岩は君を荒涼とした場所へ運んだ。なぜなら、君の中の誰かがもう一人の君に過剰に呟き続けていたからだ。もし君が囁いていたら、今こんな荒廃した場所にはいなかっただろう。彼らは君を見逃したはずだから。今、君が見える。人間味を完全に失った小さな部屋が目に浮かぶ。ベッドと鏡以外の何も置かれていない。
今や君を無限に占めているのは、その鏡なのだ。
どうやって監視者に外部との通信を許可させたのかは覚えていないが、何年も前にその小さな部屋に収容されたにもかかわらず、それが可能になったのはほんの数ヶ月前のことだと知っている。
それでも、通信の経路が開かれた後、あなたはすぐに連絡を取ろうとする者たちに応答しなかった。おそらく少し不安を感じていたのだろうし、監視者を大いに信頼していたわけでもなかったに違いない。
君が直接私に連絡したことは一度もないと思う。実際、君が私の通信を実際に受け取ったという確かな証拠は私にはない。ただ、君が目の前のガラスを絶え間なく磨き続けている姿——あるいはそう想像している——が見えるだけだ。まるでそれを磨いて消し去りたいかのように。そして磨いていない時は、自分の姿を交互に賞賛し、そして睨みつける姿を想像できる。その姿に永遠の混乱を抱きながら、時には愛撫し、時には毒舌だけを浴びせている。
あなたは監視者たちがほとんどあなたに関心を示さず、実際は栄養状態を保つためだけに存在するとほのめかした。彼らは肉体的にあなたを生かしているだけで、それ以上は何もしていない。
少なくとも時折は、あなたの更生のために世話役が姿を現すだろうと思っていたが、それどころか、彼らは進んであなたと、もう一人のあなた——今や鏡の中で無造作に賞賛したり呪ったりできるあの人——を好き放題にさせておいている。まるで、あなたが経験した全ての後でさえ、あなたの監禁理由など取るに足らないものだったかのように。
だが鏡こそが、実はお前の始まりであり終わりなのだ。お前がそれを粉々に砕いて忘却の彼方へ葬り去りたいと願う真の理由はここにある――お前自身が存在しなくなるためだ。つまり、ついに、取り返しのつかない形で、お前は自分自身と、今や消え去ったもう一人の自分を、不思議なことに永遠に、水平に、この小さな部屋の果てしない夜の床へと結びつけるのだ。
この新しすぎる電話!こんなモデルは見たことがない。閉回路のようだ。まるで独り言を言っているかのようで…
2013年2月9日
警視』ロバート・フラー著
警視は忙しかった。電話が鳴りやまない。ようやく受話器を取った。
「ゴーデオか、誰だ?」
気まずい沈黙が続いた。やがて臆病な声が聞こえた。「重要な情報があります」
「どんな内容だ?お前は誰だ?」
「それは明かせません。しかし非常に重要です。あなたの事件に関するものです」
「誰も知らない。厳重な極秘事項だ」短い間を置いて「どんな情報だ?」
「私は詳しい。君の調査を見た」
「何を聞いた?」
「君はデマを調査している。史上最大のデマだ」
ゴーデウ警部は衝撃を受けた。しかし黙っていた。「ああ、そうか、話してくれ」
「匿名性を保証してくれ。この通話の追跡は不可能だ」
警部は激しく囁いた。「約束する」
「まず教えてくれ。なぜこの偽装を暴く? 君の真の目的は?」
「君が説明しろ。なぜ気にする? なぜ助ける? 暴けないのか? そんなに詳しいくせに…」
「協力しようとしている。君が難癖をつけている」
「何かくれ。ほんの小さな手がかりでもいい。誠意の証だ。そうすれば喜んで協力する」
「わかった、ここにある。ほんの小さな断片だ。証拠を見つけた。君の理論は?なぜ関わる?」
「どんな証拠だ?」
男は激怒した。怒りを爆発させた。「なぜそんなに難しいんだ!?要求を聞け。さもなくば切る」
ゴーデオ警部は態度を和らげた。一息つく必要があった。これがチャンスかもしれない。「善意の話をしただろう。人類は騙されてきた。山ほどの嘘を吹き込まれてきた。だから俺の説はこうだ。何世紀も前のことだ。陰謀があった。詐欺を働くための陰謀だ。彼らはでっち上げたんだ」
「ああ、そうか、それはいい。そして俺には証拠がある。場所も知っている。どうぞ続けてくれ」
「彼らは欺こうとした。人類を誤った道へ導こうとした。だからあの本だ。一部は真実だった。歴史的事実に基づいていた。検証可能な事実だ。それが餌だった。人々を惹きつけた。蛾が電球に飛び込むように。レミングが崖へ駆けるように。子供たちが笛吹きに導かれるように。抗えなかった」重い沈黙が流れる。「では、その場所はどこだ?何の場所だ?」
「まだ隠している。なぜ君が特に?個人的に被害を受けたのか?立証できるのか?法的な立証だ。裁判官が認めるような」
彼は冷静を保った。だがゴーデオは激怒していた。「ここは法廷か!?」重い囁き声で。そして続けた。「お前が裁判官か?陪審員か?死刑執行人か?一体全体何なんだ!?」
「冷静さを失っている。何の得にもならない。質問に答えろ」
彼は考えた。自分の立場は?傷ついたのか?法的立場は?
「時間をかけている。我々に時間は無い。これは緊急事態だ。明るみに出さねば。手遅れになる前に。早く進め…」
ゴーデオは新たな手を使った。逆心理のようなものだ。彼は何かをでっち上げた。そう思った。「洞窟があった。コウモリで埋め尽くされた。彼らの隠れ家だ。入り口は隠されていた。古代の文書がこれを証明している。まだ見つかっていない。宝の地図かもしれない。『X』がその場所を示す。全てが秘密裏に。人々は沈黙を誓っていた。それが奇妙だった。彼らは何か深遠なことを知っていた。なぜ秘密結社なのか?なぜ隠すのか?」
電話は静まり返った。かなり長い間。かすかなブーンという音。かすかにブーンという音。盗聴されている!?誰にもわからなかった。ついに男が口を開いた。「その通りだ。洞窟だった。コウモリはいたるところにいた。それが問題だった。秘密のことではない。彼らは何も隠していなかった。全員が感染した。彼らは入り口を塞いだ。世界が危機に瀕していた。彼らは皆、自らを犠牲にしたのだ」
「意味がわからない。どうやって知ったんだ?」その時、何かがはっきりとわかった。彼はコウモリだった。そして逃げ出したのだ。全ての証拠と共に。だから知っていたのだ。洞窟の場所を。ゴーデオは彼の名前を知っていた。頭文字は『D』。そして『D』は感染していなかった。彼が感染源だったのだ。
『D』は全てを知っていた。その時、ドリルの音が響いた。電話の向こうから。小さな穴が二つ。電話は血まみれになった。
2023年9月12日
幕が下りる』ロバート・フラー著
彼は遮断を感じた。人生という舞台の上で。そしてそれは決して消えることはなかった。専門医に目を診てもらった。
一人。また一人。さらに何人か。そしてさらに。やがて多すぎて。数えきれないほどの専門医が。皆がほぼ同じことを告げた。視力が衰えていると。
それでも彼は舞台に立っていた。自らの劇を演じながら。そして誓った。見られると。誰も彼の演技を止められないと。
その時…彼は見た。真実を見た。そして真実が彼を解き放った。自由になり、自分が本当にいる場所を見据えた。闇の力が彼を台無しにしていた。だから誰も彼を見なかったのだ。
誰かが彼を舞台裏で襲った。犯人は誰か、彼は知らなかった。劇が終わると、それは落ちた。
ガーゼの布だ。彼が隠された。彼は影のような存在だった。そのガーゼの布にほぼ覆い隠されていた。この状況には、どうしても理解できない要素があった。なぜ彼は、この舞台で繰り広げられるはずの実際のドラマの背景に過ぎないのか?
しかし、何かがはっきりしない。別の何かが起きている。彼は別の理由で遮られていた。誰かが舞台裏で糸を引いている。
何が起きている?何が起きていて、なぜなのか?彼はすぐに、それを告げる夢想に陥った。彼に、知る由もないことばかりだと告げた。この舞台での人生は、彼がこれまで思っていたものとは全く違っていた。全くもって。ゲームのあらゆるレベルで常に多くの見えない力が働き、それらは全て、彼を彼の役柄を演じさせまいと積極的に謀っていた。彼らは彼の役柄を彼にふさわしくないと考えていたのだ。
だが彼の役割とは何だったのか?彼は単なるエキストラに過ぎなかったのか?それとも、彼ほど重要で替えの利かない存在とみなされていたのか?舞台裏の奥深くで、長い間、ざわめきが続いていた。彼は二度も、ほとんど眠りそうになった。
彼は弁護人に相談した。有益な助言は得られなかった。布のガーゼの陰に身を隠した。すると誰かが再び彼を引きずり出した。
法廷が再開された。裁判官は激怒していた。こんな事態は見たことがないと言った。被告人こそが、まさにその罪を犯した張本人だったのだ。
彼は弁護人の助言に反し、自ら証言した。弁護人はガーゼの布について、それが果たした役割について尋問した。
沈黙が訪れた。被告は肩をすくめた。何を言えようか?自らにこんなことをするはずがない。
それでも疑念は残った。陪審員は納得していなかった。彼らはこの光景に惑わされなかった。誰かが陰で動いていたのだ。
誰かが。だが誰だ? それとも何か? いったい何だったのか?
誰かがカーテンコールを受けた。しかもずっと後になってから。芝居はとっくに終わっていた。それでもなお誰かが注目を欲しがっていた。
誰が? なぜ? 何のために? どんな目的で?
彼は閉塞感を覚えた。今またそれが起きている。そして決して消えることはない。彼は大声で、抑えきれないほど叫び始めた。
2024年2月13日 [17:43-18:53]
ザ・エクストラ』ロバート・フラー著
モーティマー・ダルトン——皆が彼をモートと呼んでいた——はセット内を自由に動き回ることができた。舞台裏全域はもちろん、果てしなく広がる峡谷、溝、谷、岩層の景観など、その眺めは彼の想像力を超えたほど遠くまで続いていた。
モートは通常、撮影現場や舞台裏、制作陣が現在使用していない広大な隣接する荒野エリアを自由に歩き回る冒険以外には何もせず過ごしていた。現場での彼の出番が必要な際のスケジュールは事前に通知され、発表されたスケジュールから外れることは稀だった。予期せぬ呼び出しが必要な場合でも、携帯端末で容易に連絡が取れ、責任者からは必ず十分な事前通知が与えられていた。
しかし勤務時間の大半——彼はプロフェッショナルとして常時待機状態にあることへの報酬は実に手厚かった—— 彼らは彼が仕事を確実に遂行できると信頼しており、彼は常に期待に応えていた——彼は浅い墓が並ぶ墓地や、酒場、ホテル、貸馬車屋、雑貨店、食堂などが並ぶ小さな西部風の町の外観をさまよっていた。モートは、こうした町が間もなくこの地域に点在する無数のゴーストタウンの仲間入りをすることになるだろうと確信していた。たとえそれらの外観だけの町がせいぜい架空のものであったとしても。
さて、実際の仕事内容——一日のうちほんの数分しかかからない作業——を考えると報酬は比較的厚かったが、決して楽な仕事ではなかった。決してそんなことはなかった。彼は、この仕事がより儲かる仕事への足がかりになるのではないかと夢想しがちだった。おそらくは現在よりも脚光を浴びる仕事か、あるいはむしろ、彼が特に憧れていたポジション——カメラの後ろ側、いわば舞台裏の仕事かもしれない。
「もし他のスタッフに自分の実力を示せたら、構図の創造性を存分に披露する機会さえ与えられれば、彼らは間違いなく私の真価を見抜くだろう」と彼は考えた。
しかし現実は、彼の仕事の大半は目立たないことだった。カメラの前で本物のアクションが繰り広げられる間、彼は背景のどこかに潜む幽霊のような存在でしかない。それでも彼は、この仕事をする者が必要だと理解していた。だからこそ、プロとしての誇りを強く持っていたのだ。
それでも、彼の心と脳裏を駆け巡る衝動は消えなかった。たとえ正気を保つために、あるいは正気を失う代償を払ってでも、必死に抑え込もうとしたにもかかわらず。
だから、特に冬の寒さが厳しい季節や場面では、彼は雪に覆われた野原に散らばる黒いカラスたちを、意識的に見つめるようにしていた。鋭いくちばしで絶えず彼を叱責するかのように、まるで敵対者か宿敵であるかのように。彼らは、鳥類の優れた知性で彼に向けて発する、かすれ声で最も鋭い「カーッ!」に至るまで、その存在のあらゆる側面に対する彼の深い愛と賞賛を、まったく理解していないようだった。そして彼らが気づいていなかったのは、彼が彼らを完全に理解していたこと——おそらく彼ら自身よりも深く理解していたことだ。
こうした遭遇を重ねるうちに、彼は自分が彼らの神秘的な映画における単なるエキストラに過ぎないと感じるようになった。だから彼は、彼らに主役の座を奪われないよう、風景の中に溶け込むべく全力を尽くした。
ちょうどその時、撮影監督の緊急の呼び出しがあった。彼はすぐに必要とされ、数ある衣装の一つを急いで着なければならなかった。時間通りに戻るためには、本当に急いで戻らねばならなかったのだ。カラスたちが一斉に、モートがこれまで聞いたこともないような激しい不協和音で鳴き始めた。しばらくの間、彼らは悪意や悪戯心で自分を尾行しようと謀っているように思えた。彼らが全く気づいていないであろう、深い敬愛と愛情を抱いているにもかかわらず。しかし彼らは引き下がり、彼は息を切らしながらも、すぐにセットに戻ることができた。
幸い衣装の着替えは簡素で迅速だった。衣装係は早着替えのベテランであり、モート自身も万一の事態に備え、常に顔に十分な化粧を施していた。
しかし今回、この衣装が異例だったのは──このクルーと仕事をしてきた中で前代未聞だったのは──彼が完全な道化師の装束をまとわねばならないことだ! この状況下で、どうやって注目を集めないようにすればよいというのか?
しかしクルーは、酒場の奥深く、ピアノ奏者がひどく調律の狂った楽器でラグタイムを叩き鳴らしている場所の近くのテーブルに、椅子を用意した。その楽器は明らかに全盛期を過ぎていた。
そこでモートは思った。「これは茶番だ!罠だ!まったく不公平だ!」
そしてモートは台本にない行動で主役を張ることを決意した。
今こそ彼の出番だ。彼は威風堂々と主役のガンマンの横を通り過ぎ、栄光の瞬間を迎えた。その頂点は、騒がしいカラスの軍団全員を副官に任命した時に訪れた。今こそ彼らが、モートがどれほど深く彼らを愛しているかを理解したのだ。そして彼らは応えた。
2024年2月14日 [11:55-12:57]
聖杯』ロバート・フラー著
エスターは裏庭にある自分だけのオアシスで、カラリリーを眺めていた。柔らかくしなやかで、ベルベットのような純白の花杯が、聖餐の秘められた泉の奥深くから官能的に覗かせる黄色い花穂。まるで恵みをもって捧げられた井戸のようで、その裸のようでいて、同時に「アラム」とも呼ばれる花――それは「裸」と「賢明」の両方を意味する。
彼女のプライベートガーデンは好みにぴったりだった。人里離れたその場所は、彼女の本性通り、普段はほとんど一人で過ごすのに適していた。時折訪れる祝祭的な瞬間こそが格別で、その時は奔放に身を委ね、レミの星がヒノキの木の下で輝きを放つ。オリーブの庭に祝福された暗い道が、その光を導くのだ。
そして彼女は思った、自分のアロエは余りにも現実的だと。かつて西部劇で見たワイン容器とは違い——表面は宝石をちりばめた黄金の器に見えたが、実は全て偽物で、特定の信仰者にとってのみ価値を持つ象徴的な幻影に過ぎなかった。
その器は本物に見えるよう金メッキされ、一見宝石らしきものは大半がガラス製で、より高価なものを模して彩色・成形・装飾されていた。だが彼女は、この聖杯——偽りの姿を装うこの杯——に宿る祝福を思い出した。それは聖なるぶどうの守護者サン・ジュゼッペが授けたシチリアの祝福であり、その実が聖餐の血となるぶどうを育むものだった。
マルチェッロはアコーディオンを弾きながらイタリアオペラを歌い、この上なく無邪気な男だった。彼の真の宝物は故郷から持ち込んだ丘の葡萄の挿し木であり、新世界の土壌に移植して、彼と家族が故郷で捨てた生活を続けられるようにと願っていた。
しかしこれらの挿し木には聖人の祝福が必要だった。聖人によってその目的のために力を与えられた聖域の中で。そして彼が携えていた聖杯の幻影こそが故郷への直接の繋がりであり、その象徴的価値はほぼ完全にその繋がりが表すものに依存していた。
しかし夢想にふけるエスターは、むしろ自身のプライベートガーデンで起きている現実の出来事に強く意識を向けていた。そして彼女はアロエの持つ力、魅力、祝福を感じ取った。
何しろ、純白の結晶のようなベルベットの輝きを放つこれらの花は、裏切ることも、害をなすことも、ありのままの姿以外の何者にもなれなかったのだ。
そして彼女は、はるか北の小さな海岸の町で、険しい崖に咲くカラリリーを見つけた時のことを思い出した。それらの花は、花序軸の真の黄金のすぐ隣で、花被の中に潜む、ゆっくりと螺旋を描く軟体動物を宿していたのだ。
しかしこれらの単殻類は、実は小花の内なる秘め事を糧にしていたのだと彼女は思った。彼らはそれを栄養として吸収していた。つまり隠れているというより、苞葉と肉穂花序を吸い尽くし、花を軟体動物へと変容させていたのだ。
それは一種の動植物の錬金術であり、互いの境界で支え合う緩やかな螺旋の聖なる舞踏だった。形が移り変わる様は、この神秘的な生命の真髄を思わせずにはいられない。そしてそれが、彼女にとって最も愛おしいものだった。
2024年2月15日 [11:59-13:38]
贈り物』ロバート・フラー著
彼にとってそれは不思議な物だった。何十年も前に、最も親しい叔父の一人から贈られたブローチだが、今までその意味に気づいたことはなかった。
そこには、まさに二体のレプラコーンとしか言いようのないものが刻まれていた。左側のレプラコーンは、偉大なるホームズだけが扱えるような手持ちのルーペを手にしていた。
そのやや大きすぎるルーペは、まるでクリンク大佐があの風格で身につけていたように、右目の上に載せられていた。そしてあの帽子! 明らかにシャーロック・ホームズ風だった!
その法医学的・論理的推理の達人のすぐ左に立つ小柄な小人、おそらくワトソンだろうが、いずれにせよ彼は小悪魔的な風貌を完璧に体現していた。
言うまでもなく、この小柄なレプラコーンが欠点なく忠実であるだけでなく、気まぐれに風車を追いかけ虹の金の元へ駆けるように見えるのは、初歩的な推理で明らかだ。
だから、彼の愛する叔父が贈ったものは、まさに虹と宝を追うよう促すハートピンだったのだ!必要な手がかりを見つけ解読せよと!
そして何十年もかけて、この紋章が明らかに告げていることにようやく気づいたのだ!隠された細部まで見抜き、それらを組み立てることに。
そして、彼の忠実な相棒がすぐそばにいたのだ! そんな精鋭チームを前に、ついに彼は悟った――事実上、何でも可能かもしれないと。そうして彼は夕暮れの中へ歩き出した。
しかし、彼のそばに付いてくる者は誰もいなかった。あの小悪魔は今、一体何をしているんだ!? 酔っ払いのろくでなしが牢屋に放り込まれていないか確かめるため、彼は地元の警官に電話をかけた。
警部は断言した。自分を含め同僚の誰も、そんな男を見たことさえない、ましてや逮捕したことなどないと。
そこで彼は今や想像上の友と共に、今まさに満月へと輝きを増す月へと、気ままに歩き続けた。遠くで狼男が遠吠えした。
やがて新たな使命に倦み、近くの酒場へ入り、気力を整え方向を見定めようとした。不思議なことに、路地裏の向かいにある薬屋はまだ開いていた。
店主に対し、不整脈に効く薬はないかと厳かに尋ねると、彼女は同様に厳かにキツネノテブクロを強く勧めた。彼は嬉しく思った。
不整脈に関する彼の言い訳は当然ながら策略に過ぎない。暗闇の中で無礼にも彼を見捨てた分身(ドッペルゲンガー)を、いかに早く葬り去るかに執念を燃やしていたのだ。
彼女は親切かつプロフェッショナルに薬を調合し、正しい使用法についての一般的な免責事項を説明し、さらには優しくて愛情深いほどに、彼のために包装までしてくれた。
彼は今や相棒を探す準備ができていた。信頼に足らない、放浪騎士でありならず者の相棒――サンチョ・パンサであれ、フランク・バイロン・ジュニアであれ、あるいはブルウィンクルの相棒ロッキーであれ。
そして心の砂漠を横断し、どこに隠れようとあの悪党を見つけ出すまで、ユーラシアのトゲ草を追いかけるつもりだった。転がる枯れ草は全て、罪人にキツネノテブクロをもたらすのだ。
しかしその時、彼は最も愛した叔父を思い出した。叔父が常に体現していた自然なユーモアと善意だけで、いかに容易に彼に与えてくれたかを。
記憶の奥深く忘れ去られた場所に、重大な意味を持つ音楽が響き渡った。まるで魔法の呪文のように、彼を正気と優雅さという天性の才能へと誘い戻すかのように。
そしてまさにその時、彼の探求はついに終焉を迎え、心はこれまで見たこともないほど広く、高く開かれた。
2024年2月16日 [12:59-15:23]
ポータル』ロバート・フラー著
雨の止まない日だった。薄霧と小雨が交互に降り、時折激しい雨が降り注ぐ。そんな日は厚着をして、心地よい椅子に丸まり、選りすぐりの本と小さなポートワインの杯を手に過ごすのにぴったりだ。あるいは、ただぼんやりと窓の外を眺め、冷たいガラスを伝う雨滴を何の気なしに見つめながら、時間を過ごすのもよい。こんな日には、窓が意識の表層の下に潜む謎を解き明かす通路になるのではないかと、時に想像した。
視界をぼんやりとぼかすと、光が耐え難いほど輝き、頭全体が柔らかなエネルギーの輝きに包まれ、それ自体と一体となる感覚に襲われることもあった。ある者は、これこそが「あの場所」への道だと語った。あの場所は別世界でありながら、現実的にはこの場所と何ら区別がつかないものだと。また、様々な雑念で満たされた日常の意識が純粋なエネルギーによって洗い流される瞬間こそが、強大な共感を導く門戸だと語る者もいた。その共感は極限まで高まり、時空を超えたあらゆる距離において、他の無数の生き物の歓びや悲しみ、苦痛や恍惚を体感できるほどに。
マヤにとってこの日は、特に何もない休息と空想に満ちた日だった。しかし雨が激しくなるたび、彼女が「渦」と呼ぶものに強く引き込まれていくのを感じた。幼い頃から周囲の人々と深い精神的な繋がりを持っていた彼女にとって、これは馴染み深い状態だった。
こうした状態は慎重に対処する必要があった。脆弱な人間の心と精神が耐えられる強度の限界があるからだ。ポータルの縁に足を踏み入れるのは一つのこと。適切な警戒心を欠いたままさらに深く入り込むのは、危険極まりない行為に等しい。
しかしこの日だけは、数十年にわたる経験の中でも異質だった。他の場所や人物から彼女へと注ぎ込まれる感情の強さゆえに、彼女は精神病的な発作の境界線にある夢想へと滑り込んでいくのを感じた。
特に目にしたある光景は極めて残酷で、このレベルの強烈さと闇が湧き上がるときは、必ず脱出路を見つけねばならないと悟った。彼女はこれまで、このような現象を恐れたことはなかった。それでも、彼女の内側で制御不能な震えが始まった。この窮地から抜け出す方法はただ一つ。意識的な呼吸を一つ一つ、感情を込めて深く吸い込み、輝くエネルギーの輝きが頭と心と魂を満たし溢れ出すのを許すことだった。すると雨が止み、彼女は全てを洗い流された。静かに夜の空へと歩み出ると、切れ間のある雲の間から満月の陶酔的な光線が彼女を包み込むのを感じた。窓が開いた、そして彼女自身も開いたのだと。
2024年2月17日 [18:53-19:53頃]
ザ・フライ』ロバート・フラー著
私は貴族の家系に生まれました。貴方の1700年代半ば頃以前の記録はかなり断片的ではありますが、貴方の尊い分類体系において我々が栄光に満ちた、親しみやすい名称を授かった時、我らコバエ(Musca domestica)は、単なる3500の寿命をはるかに超える誇り高き歴史を有しています。もし知りたいなら、我々の祖先は7億5千万世代以上に遡る。記録が最近になって始まったのは残念だ。マンモスやマストドン、有袋類や哺乳類、ボリアエニド類や鳥類、そして貴方の祖先の裏庭に生息した霊長類について、我々が語れたであろう物語を想像してみてほしい。あの壁に張り付いた諺のハエが何を語れたことか!
現在私は、名門研究施設に収容されている。その施設は内部の機密性ゆえに表舞台を避けている。実際、その名称「ムスカリウム」を知るのも一苦労だった。外部にはほとんど知られていないが、我らムスカリウムの収容者は、白衣の連中が何をしているか熟知している。知らぬはずがない。何しろ我々こそが、彼らの様々な実験の被験者なのだ。
ムスカリウムの迷宮のような施設内には数十の異なる棟があり、我々収容者はその大半が最も侵襲的で、過酷で、狂気じみた拷問手法を用いていることを痛感していた。昼夜を問わず仲間の収容者たちの悲鳴が聞こえてきたが、我々にできることは何一つなかった。
ごく一部の白衣たち──ほんの一握りだが──は被験者に対して、実際に気遣い、何かを感じていた。この施設全体で最もエリートで憧れの対象だった棟は、音楽実験を目的とした電極の使用に特化した棟だったのだ。
私はこう信じたい——蛹から脱皮し成虫へと変態する過程で、あの翼へ送られるべき理由を、責任者たちに熱心に訴えたからだ。今まさにあなたの脳へ思考の断片を送り込んでいるこの成虫へ——耐え難い拷問と確実な滅亡ではなく。
先述した貴族的な血筋とは、単に家蝿の遺伝子プールに属していたというだけでなく、より正確には、中東の音楽活動が最も盛んな地域において、著名な音楽家一族の城や粗末な住居に祖先がいたことを指すのだ。我らは皆、その才能を受け継いでいた。常にあらゆる旋律とリズムに耳を澄ませ、その音楽様式の大御所たちが紡ぎ出す音に完全なる共鳴をもって、羽を調和させながら羽ばたいていたのだ。
しかし、なぜ私がムスカリウムのあの特定の棟にたどり着いたのか——率直に言えば、単なる偶然の産物だったのかもしれない。あるいは、より敏感な白衣たちが密かに若鳥たちのオーディションを行い、単なる平凡な個体でその翼を満たすのではなく、真の生きた才能を見つけ出そうとしていたからかもしれない。彼らの中には実際に音楽の耳を持っていた者もいたように思える。
いずれにせよ、私はその翼に居る資格が十分にあると自負していた。血筋そのものがその証左だった。そして結果的に、マックスというあだ名の特定の白衣が私に即座に好意を抱き、その事実を同僚に打ち明けることさえあった。
マックスと彼の親しい仲間たちは、研究用機器を最大限に活用し、被験者たちのおかげで(当然ながら)最も深遠な聴覚体験を全員で享受する方法に、純粋な好奇心を抱いていた。
そこで彼らが取った手段は、想像しうる最小の電極を数多く、私たちの神経中枢に細心の注意を払って装着することだった。さらに多種多様な動作センサーも設置されたが、その詳細を説明するのは到底無理だ。そして最も精巧だったのは、特殊なセンサー群だ。これらは可能な限り広範囲の活動を監視するために用いられた。対象は我々の各視覚野(複眼と単眼の両方)内だけでなく、同様に重要な、偽気管を介して生命を維持する摂食活動までもが対象だった。
ご覧の通り、彼らの装置には無数の入力と出力が存在し、それらは全て最終的な聴覚的成果を豊かにする役割を果たすに違いない。
私は彼ら、特に私の要求をかなり注意深く聞いているように見えたマックスに、音楽における私の得意分野はピアノ、そしてキーボード全般であることを知らせようと最善を尽くした。だから最初の接続、最初の接続先がピアノ(もちろん電子ピアノ)だと気づいた時は有頂天になり、すぐに自慢し始めた。同僚の何人か、そして白いコートを着た者たちさえもが不快に思うほどに。
最初の演奏はラヴェルの『鏡』から、夜蛾を題材にした小品だった。当然ながら、白衣の集団の中に一人の道化師がいて、私の見事な演奏の後で、ベラ・バルトークの『ミクロコスモス』から「ハエの日記」という小品をリクエストしてきた。冗談じゃない!しかし私は謙虚に、そして忠実にその要求に応じた。もっとも、その後すぐに同じ巨匠のピアノ協奏曲第2番から厳選した抜粋でフォローアップしたことは付記しておく。
紳士的なマックスはすぐに私の腕前を試そうと、即興で何ができるか試した。その実験の最中、私はもちろん演奏に没頭していたが、視界の隅でスタジオの聴衆が私の演奏に大いに盛り上がりを見せているのがわかった。
実はこの実験は後世に残すため記録されていた——いや正直に言えば、全ての実験が記録されていたのだが——この演奏こそが私のキャリアを飛躍させた。その後は全てが変わった。即座に一流のエージェントと契約し、SNSアカウントにはあまりにも多くの反応が殺到したため、少なくとも1、2時間は投稿を停止せざるを得なかった。
こうした一連の出来事の結果、私の新しいエージェントは、我々が直面している時間的制約を十分に理解した上で——最良の実験室環境下でも、私が45日以上生き延びるとは期待されていなかった——カーネギーホールでのデビュー公演を手配した。
それは比類なき前代未聞のキーボード祭典となるはずだった。複数の標準電子キーボードに加え、ノード・リード2のような最高峰シンセも揃い、私はこの宴のトップバッターを務めることになっていた。
残念ながら両親は来られなかったが、親族の多くが会場には来られなくても、必ずライブ配信を観るよう手配してくれた。
それは私が短い人生で待ち望んでいた瞬間だった。観客全員が人生最高の音楽体験に備えていた。マックスは全ての接続を二重三重に確認し、本番の数時間前にはミニリハーサルも済ませていた。
そしてまさに私がステージに車椅子で運ばれたその時、大規模な停電が北東部の大部分を襲ったのだ。
2024年2月18日 [13:44-15:47]
種』ロバート・フラー著
私たちは森の中を歩いていた。それはごく普通の日のようだった。しかし足元にはエネルギーの奔流があった。これは実は全く予想外ではなかった。私たちは次第に敏感になりつつあったのだ。
足元のエネルギーは極めて微細だった。私たちはそれを捉えきれなかった。それでも一歩また一歩と、私たちはそれを踏み越えていった。次第に私たちはそれに気づき始めた。この神秘的な存在が何であるかを。
私たちは様々なことを話していた。どれもその謎についてではなかった。それでも何時間も一歩一歩歩き続けた。私たちが踏みしめていたのは大地だった。そして足元には私たちが求めていたものがあった。
やがて小雨が降り始めた。地面は次第に少し湿り気を帯びてきた。それでも私たちはその秘密に気づかなかった。都合の良いピクニックテーブルで立ち止まった。近くにせせらぎが流れていた。
ワインとチーズを楽しんでいた。やがてそれが私たちの体験の全てとなった。それでももっと多くの楽しみがあったはずだ。一人は流れ落ちる水を撮影し、もう一人は枯れ葉を弄んでいた。
やがて雨が少し弱まり、太陽が私たちを照らし始めた。それでも私たちはその光に気づかなかった。頭上に虹が現れ、その色が全てに染み渡り始めた。
足元にもっと多くのものに気づき始めた。全てがどういうわけか、より生き生きとしていた。だがなぜ最初から気づかなかったのだろう。霧雨が戻り、私たちをじわりと濡らし始めた。
芽やキノコが姿を現した。土を突き破る小さな命の芽。それでも私たちはまだ雑談を続けていた。種や胞子はなおも突き出していた。私たちは次第に沈黙に浸されていった。
言葉が尽きかけていた。足元には明らかな成長がまだ多くあった。それでも増す沈黙は十分ではなかった。ただ一歩一歩歩くだけ。そしてまた別のピクニックテーブルを見つけた。
今度はより注意深くなった。食べ物とワインが増え、私たちはリラックスした。それでもまだ気づいていない何かがあった。ロビンは最初からずっと歌っていた。小川はゴボゴボと音を立てていた。
私たちは気づくことを決意した。深く瞑想するように座った。それでも真実を捉えられなかった。足元にある真実を。常に魔法のようなことが起こっていたのだ。
やがてそれが浮かび上がってきた。足元の闇の生命は常に成長していた。しかしそれは意識から隠されていた。根源的な原理が働いていた。種こそが鍵だった。
私たちは腐敗する物質について語っていた。それが種と成長を養う方法について。それでもなお理解できなかった。足元で起きている数多くの事象。そしてそれらが完全に隠されていること。
その複雑さは理解不能だった。種が発芽しようとする生来の衝動。しかしこの成長のすべては、どういうわけか恣意的だった。なぜある種は特定の形に、他の種は別の存在へと変わるのか。
私たちは自分自身として歩いていた。自分たちがどれほど恣意的であるか、ほとんど気づかずに。それでも私たちとなった種は私たちとなった。そして存在することこそが私たちの義務だった。恣意的に与えられたままに存在すること。
すると小雨が再び降り出した。私たちの散歩は湿ったエネルギーに浸された。しかし、どうしてこんなことが可能なのか。またしてもピクニックテーブルに出くわした。チーズとワインが謎に燃料を注いだ。
私たちは…
2024年2月19日 [01:44-03:04]
かつて私たちは』ロバート・フラー著
高地の砂漠に佇むゴーストタウンを想像してほしい。風雨に磨かれた石造りの建物、時と嵐と風に晒された木製のスラット。かつてそこにあった生命は、銀の時代を偲ばせるやせ細った骸骨へと変貌した。リンカーン以前のペニー硬貨一枚で、四分の一ポンドのチーズや米、あるいは「ペニーキャンディ」をたっぷり買えた時代のことだ。
丘の頂と峡谷、ジュニパーとパイニョン、低木と湧水、花崗岩の野原と断崖、そして華やかな生活と好景気――それが続いた限りの間。それはアイルランド人の幸運が頂点に達した、水晶の泉のほとり。蜃気楼はわずか6年ほどで、銀脈が枯れると同時に消えた。だが元来ここは岩絵の土地だった。
四つの生を生きる蝶は、幸福へと至る旅路で永遠の命を持っていた。だが郵便局はそんなものを届けたことは一度もない。ヒマワリ、太陽神、陽光、雨、交差する道——すべては夢の時間へと導く。だが、ユッカもウチワサボテンもクリフロースもトゲトゲ星も何と言おうと、このすべてが鉱石のために冒涜されたのだ。
イエルバ・マンサを夢見る砂漠のマリーゴールド、アプリコットマロウ、ライラックサンボンネット、あるいは砂利の亡霊。銀灰色のヴィレオ、サルビアブッシュスズメ、ジュニパーチチブ、青灰色のムシクイ、そして何より小さなチドリが、乾いた野原を飛び交い、オオミズナギドリがオオクチバス、コンヴィクトシクリッド、タイガートラウト、グリーンサンフィッシュを捕らえる夢を見る。
だが侵入者たちにはそんな夢などなかった。ただ瞬時に富を得る夢だけだ。東を離れこの神に見放された地に、一攫千金を夢見てやって来る前に聞いた噂話のような夢を。彼らの通貨は銀貨だったが、朝のコーヒーを淹れる際に指の間からすり抜けた銀魚と何ら変わらなかった。
鉱脈は罪よりも早く枯渇し、鉱脈は塵と化した。だが、鉱夫たちが無益で無意味な宝を求めて大地を掘り起こす前からそこにあった生命は、まるで彼らが掘り起こしたかのように続いていた。彼らの果てしない探求、手に入れられないものへの欲望、この地上に実在しないものへの渇望が染み込んだ宝を求めて。
銀魚は真実を知っていた。トカゲやキングスネーク、ナイトスネークも騙されなかった。雲母帽、パフボール、地衣類、シャギーマン、インクキャップは、ただそこに留まった。そして、ペインテッドレディ、ウエスタンピグミーブルー、クイーン、ホワイトラインドスフィンクス、ブルーダッシャーは、何の憂いもなく青空へと舞い上がった。
こうして人間の社会を模した試みはほとんど消え去った――石と、ほぼ枯れかけた木の板と、あの神秘的な岩刻画と、地球の終わりまで消えるつもりなどなかった風景だけが残された。丘の方を見れば、左に煙突のある一つの建造物が、眼鏡をかけた誰かのように見えた。
では、人間の血を引く者で、今もこの丘や峡谷を彷徨っている者はいるのか? 彼らの貪欲や放蕩、あるいは放浪や冒険の物語を語る者は、もはや一人も残されていないのか? そして最初にここに住んだ者たちの物語は? ああ、彼らはすでに語り終え、後世のすべての世代のためにそこに刻み込んでいた。そして動植物たちは、そのことをよく知っていた。
2024年2月20日 [17:40-19:23]
カルーセル』ロバート・フラー著
入口の看板にはただ「ファンハウス:家族みんなで楽しめる」と書かれていた。しかし、一部の人々が「祭り」と呼ぶこの場所の所在地は、記録上最も辺鄙な郡の一つにあった。
敷地内には少なくとも七つの回転遊具があった。正確に数えるのは困難だった。敷地全体が、より面白く見せるために無数の光のトリックや鏡の仕掛けを駆使した設計になっていたからだ。
しかしその遊具自体は、単なる水平型観覧車に過ぎなかった。子供たちを喜ばせるために、陽気な馬の装飾が加えられていた。つまり子供たちは重力と直接戦う代わりに、求心力と向き合うことになる。
それでも子供たちは全身で歓声を上げた。ぐるぐる回ることで目が回るまで楽しむ、これ以上ない至福の方法だったからだ。そして全員が気づいた――装置全体を覆うパラソルと、その周囲に少なくとも6基ある他の装置が、彼らの楽しみを取り囲んでいることに。
この日傘は、明るい日の強い日差しを遮る覆いであると同時に、幼い子供たちに特別な驚きの世界へと繋がっていることを告げる印でもあった。彼らだけが味わえる、唯一無二の驚きの世界へ。
しかし子供たちを圧倒したメッセージの重みは、日傘そのものにはなかった。いや、遊具の外縁には無数のガラス板が張り巡らされ、目の前のあらゆる光景を様々な歪み方で見せつけていたのだ。
そしてそれらのガラス板には、祭服の多色の夢のように、様々な宗教的シンボルが刻まれていた。だからガラス板を通る温かな光はプリズムを通ったかのように映し出され、まさにそのように子供たちの上に輝いた。
しかし子供たちは、まるで何の心配もないかのように、ひたすらくるくると回り続けた。鞍ごと馬にしがみつき、メリーゴーラウンドが何度も何度も回り続けるたびに、ただひたすら無邪気な歓喜に浸っていた。そこにはただ無邪気な喜びだけがあった。そして彼らはそれを叫び続けた。
子供たちや見物人に見える七つの回転装置のうち、最も中心にあるものは、やがて羽根を生やしたかのように、遠く手の届かない成層圏へ昇ろうとするかのような、次第に大きくなるブーンという音を立て始めた。
ガラスの破片が飛び散る、驚くべき音がした。それはファンハウスの中にいた者たちにとっては驚くべき音ではなかった。むしろ、これまで誰一人として聞いたことのない、まったくの未知の音だったのだ。
破片は四方八方に飛び散ったが、奇跡的に、すぐ近くにいる子供たちや様々な見物人たちをすべて避けた。それでも中央の回転木馬は回転速度をさらに上げ続け、その速度はますます激しく増加していった。
砕けた光の火花が周囲に飛び散り、中央の回転木馬は加速を続けた。たてがみが炎に包まれた馬たちが、パラソルで身を覆おうとしながら、イカロスの太陽へとますます近づいて上昇していく。
2024年2月21日 [19:40-20:40]
ガン・ブランク』ロバート・フラー著
物語の一つのバージョンはこうだ:彼らは時間と場所を約束した。しかし交通事情のため、到着時刻は少しずれた。結果として、彼らはしばしば二組ずつ、この埃が舞い上がる荒涼とした砂漠の町に集結した。実際の参加者は実に十三人いたにもかかわらず。
ケイト酒場が普段よりやや混雑していたため、最初に到着した者たちは急遽計画を変更し、遅刻者たちを新たな場所へ案内するよう酒場の従業員に依頼した。ヴォワは相変わらず上半身裸で、まるでこの場所が自分の私有地であるかのように馬を駆って酒場の正面へまっしぐらに進んだ。ベベは大きな歩幅で並んで歩いた。
その後、ヴォーヴァとベベは重い足取りで数棟の建物を抜け、街角まで来た。ロングホーン・バーの前で道路を横切り、横通りを抜けてオリエンタル・バーへと向かった。彼らはわざとホルスターと六連発リボルバーを威風堂々とした姿勢で構え、店内の全員に誰が支配者かを理解させた。二人はよろめきながらバーに入り、カウンター前に座った。
この紳士たちの雑談が理解できたらどんなに良かったか!言葉には翻訳の抜けがあるものの、目撃者の説明によると大体こうだ:ヴォワがベベに「本番の流れを先に練習して万全を期すか?」と尋ねた。しかしベベはカラオケを歌うと主張した。
不幸なことに、カラオケの時間帯はすでに全て予約済みで、賭けテーブルにも空きがなかった。二人は数分間、バーカウンターで不機嫌そうにじっと座っていたが、突然ヴォワが「おい、ダダとポンだ!」と叫んだ。人々は苦労してポンの巨体を無事にカウンターエリアに押し込んだ。
四人が揃うと、外交的な駆け引きが一気に複雑化した。ポンは即座にブラックラベルのウイスキーを一本注文し、ブラックマドゥロの葉巻をくゆらせながら、持ち歩いていたパルマハムをカリカリと噛みしめた——この非常食はまさにこうした緊急事態のために用意されていたのだ。
不幸なことに、同行者や連絡係、護衛たちは突発的な事情で足止めを食らったが、幸いにも規定通り銃器の清掃検査に間に合った。間もなくザリムとバタが到着し、続いてマーシャとアマトゥがうつむきながらおずおずと現れた。
最後の数組の客はノアの方舟のようにペアで到着した:グロッセロとラササが先陣を切り(後者はお気に入りの弾丸ブローチを優雅に身につけていた)、プルーサックと強烈な臭いを放ち、頭から熟れきったマケインが最後を飾った。信じがたいことに、プルサックは西部劇の定番衣装を拒否したため減点され、なんとグレゴール・ザムザ風の姿で現れた。
選ばれた元人物、名誉賓客はチャーターバスで到着したものの、運賃の支払いを怠ったため遅刻した。彼は何か——マーハが困惑しながら「家具購入」と呼んだもの——に足止めされたと主張した。誰も追及しない。誰も尋ねられない。誰も気にしない。
興味深いことに、この最後到着の貴賓が現れるやいなや、法律チーム、ボディーガード、おべっか使いの支持者からなる随行団に囲まれた。彼は即座に会場の真中央に座ることを主張した——間違いなく注目の的となるが、同時に全員に圧迫感を与える位置だ。
銃器検査は依然として入念に行われており、検査官は開始まであと30分ほどかかる可能性を示唆した。そこでポンは全員に酒を奢り、自身はさらに数杯追加した。彼はヴォワにキャビアの小瓶を要求し、ノーベル・ウォッカで味わった。
しかしヴォワの願いは叶わず、彼は後悔した——マハがすでにこの同胞に気づき、可能な限り媚びながらも度を越さない姿勢で彼に近づいていたのだ。この行為に龐は激怒し、銃器検査の怠慢者たちに対して即座に怒鳴りつけ、検査を急いで完了するよう命じた。
龐はヴォワらに毒蛇のような視線を向けた。ヴォワはようやくシャツを着込み、念のため手近にあったつば広の帽子をかぶることにした。この時、試合の審判団は既に集結しており、白と黒の縞模様の制服——修道服を改造したような縞模様の囚人服——を身にまとっていた。彼らは既にやる気満々だった。
しかし試合開始は当然遅れた——マーハがまたも支離滅裂な選挙演説を垂れ流し、無意味な戯言を延々と繰り返していたのだ。ポンが怒りのロケット弾のように「試合開始!」と叫ぶまで。皆は不機嫌そうに黙々と飲み物をすすり、ついに全員ガリラヤに再集合した。
随員、役人を含む全員が、葬列のように重い足取りで、水晶宮を通り、フリーモント通りを回り、ヴァージル像の角を曲がり、ポンが強く反対した肥沃な丘を越え、サムナー通りからバートフィールド通りを経て、ついに親しみを込めて「セロドボタ」と呼ばれる公共墓地の競技場に到着した。
役人たちは必須の十二角形防水布を持参した。消防車のような鮮やかな赤で、全出場者が適切な間隔を保てる大きさだった。この日傘のような防水布は、どこかフラー風の幾何学的ドームを思わせた。出場者たちは厳かに位置についた。
マハは例によって短いくじを引き、戦場の中央に配置された。十数名の訓練された対戦相手たちが、彼のオレンジジャムのような顔、入念に整えられた髪型、そして深紅の礼帽を、炎のような眼差しでじっと見つめていた。試合開始直前、役員たちは軍令のような口調で「開火」の指令を叫んだ。
三回のカウントダウンが鳴り響き、全選手が警戒態勢に入る。カウントダウン終了前、誰も銃を構えたり武器に触れてはならない。「三!二!一!」カウントダウンが終了すると同時に、十二角形の傘状競技場の周辺区域は瞬く間に混乱に陥り、全員が揃って中心部に向けて発砲した。
この壮観な光景を目撃した傍観者たちは、たとえ悔しい思いを抱えつつも、厳粛に証言するだろう——外周の射手たちはマハに全く命中させられなかったのだと!驚愕と困惑の叫び声が渦巻いた。特に傘布の隅々に散らばる「汚れた十二人組」から。
マハが事態を把握するまで丸1分かかり、無数の弾丸をかわしたことに気づくと、携行していた予備拳銃を全て取り出し、場縁に縮こまる臆病者たちへ無差別に掃射した。マハの銃技の前では、彼らは単なる砲弾の的でしかなかった。
皆が相応の報いを受けた。彼らの墓は無名のまま、罪のように浅はかに雑に積み上げられた。その後マハは沈黙のうちに深遠な砂漠へと足を踏み入れ、それ以来消息を絶った。そして鼴鼠のように付き従っていた群衆は、すぐに彼に続いて最も近い断崖から身を投げた。
法医学の専門家たちは数年にわたり事件の真相を研究した。規則違反の可能性を指摘する者もいれば、あの12人の汚い連中に偽の武器が支給されたのではないかと推測する者もいた。これは全て仕組まれた詐欺であり、入念に計画された罠で、彼らは単なる危機俳優に過ぎない——そうした論調が暗闇の反響のようにネット上で広がった。
しかし分析官の最終結論はこうだ:明確なゲームルールが定められていたにもかかわらず、大半の適格参加者が不可解にも実弾ではなく空包弾を受け取った。監督委員会は必ずやこの事態を協議する会議を開き、関係者の職は確実に失われるだろう。
この件には第二のバージョンがあり、より簡潔に語られている:13人のパン職人が東方レストランに集結した後、奥の広間にある長テーブルの宴会場を貸し切り、くじ引きで短く引いた者が中央に座らなければならないというルールを定めた。結果は前述と同様だったが、唯一料理だけが異なっていた。
2024年2月22日 [14:02-16:32]
大工』ロバート・フラー著
すべては隣人が屋根の尖った頂点に裸の胸で立っていたことから始まった。彼は真っ赤で日焼けし、長い髪と顎鬚を生やし、まるで風呂から上がったばかりのように顔に多くのそばかすのある、かなり赤らんだ男だった。その目は炎のように燃え、髪は純白の雪のように漂白され、その面貌は太陽の輝きをも凌ぎ、もし彼が口を開けば、その声は奔流の響きとなるだろう。背丈は控えめか、あるいは高く、均整の取れた体躯に広い肩幅。太陽の光がちょうど当たると、愚者の金のような肌色を帯び、足の裏と手のひらは千本の車輪の刺痕のようで、まるで七週間も無花果の木の下に座ったことなど一度もないかのようだった。それでも彼は威厳を保って現れた。体毛はほとんどなく、手足は明らかに荒れていたが。近くに住む者たちは気づいた――彼には常に小さな花々が群がり、鳥の群れがひしめき、皆が最も豊かな笛声で彼を迎え、そして彼の姉妹や兄弟である月、風、太陽、大地、火、水もまた、彼が常に最大限に祝福する存在だったのだ。そして腰帯から透ける袋に下げられた、あの神秘的な釘の壺があった。
ある者たちは推測する。この者は鷹の町から来たのだと。見張り塔の近く、枝や若芽、純粋なオリーブの芽が生い茂る場所の近く。町の近くにある窪んだ杯のようなものに包まれ、様々な廃棄物や無数の木屑が積まれた器の中に。それこそが、幼い頃にこの者が木工、彫刻、家具作りに深く魅了された主な理由だと。母は彼を止める術もなく、父――単なる代理人ではなく実の父――は姿を見せることもなかった。故に彼は抑えきれない情熱をもって新たな技を学んだ。
彼は決して名高い師匠のもとで修業したわけではない。むしろ風が行くままに、花が咲くままに、鳥が飛ぶままに身を任せ、頭に浮かんだことを何でも試すことで学んだのだ。彼のキャリア初期には、壁や台所のニッチ、そしてアルコーブや台座、本棚や引き出しをいじくり回す時期もあったが、この時期、彼は釘を死ぬほど恐れていたことが特筆される。そのため若き日の彼の主な活動は木工であった。ある時、彼は釘を一本も使わずに木だけで天井全体をフレスコ画のように仕上げた。それは見事なタイル模様で、中心から放射状に無数の木片や木屑、さらに細かな木片が奔放に広がっていた。この唯一無二の天井フレスコで得た報酬は彼を豊かにした。
次の段階では彫刻家に転じ、やがて極小細工師へと至った。その作品は精巧な光学機器と強力なレンズを用いなければ鑑賞できないほど微細なものとなった。実際、この創作活動自体が非常に骨の折れる、率直に言って苦痛を伴う作業であったため、彼は間もなく身体的負担が少なく、衰えつつある視力にも優しい仕事へと転向せざるを得なかった。
実際、この中期のキャリアは当時、彼に多大な負担をかけ、人生を立て直そうともがく数年間、障害手当を申請せざるを得なかったほどであった。こうして彼が回顧録で「暗黒の年」と呼んだ時期、彼は砂漠や生命のない場所を彷徨い歩いた。そこには多くの廃棄物処理場も含まれ、人々が想像しうるあらゆる目的のために使えるあらゆる屑を漁る姿を目にした。彼らは極貧で、絶望的でありながら、どんな犠牲を払っても生き抜こうと決意していた。
彼は一人ひとりにインタビューを始め、彼らの原動力を探った。やがて、彼らの実に多様な人生物語に魅了されるようになった。それらの物語には共通の糸が通っていたが、良心ある者なら耐え難いほど過酷なものだった。取材中、彼は決して彼らを見下したり、彼らの悩みを軽んじるような態度を見せることはなかった。彼は友人たちに説教の一言もかけなかった。しかし後年、彼らが語る彼の言葉には、当時としては稀な優しさがにじんでいた。こうして彼の言葉は時を経て、最も精巧なペルシャ絨毯のタイルや模様、渦巻きにも匹敵する複雑なタペストリーへと織り上げられていった。
友人たちとのこうした思索に没頭する傍ら、彼は狩猟や物資収集の現場に散らばる廃棄された端材にも目を留めるようになった。そこで彼は常に釘の入った瓶を携帯する習慣を身につけ、それらの端材を最大限活用するようになった。
こうして彼の木工職人としてのキャリアにおける第三期、そして最終段階が始まり、また終わったのである。
この段階はごく控えめに始まった。彼は適度なサイズの木片や板を見つけ、最初は試しに一枚をもう一枚に釘で留め、この作業がどこへ向かうのかを探りながら進めた。次第に、約6~7フィート(約1.8~2.1メートル)の長さの板と、2フィート(約0.6メートル)ほどの短い板を使うことに落ち着いた。彼はすぐに長方形の箱を作ることに熟達し、その箱は実質的に何でも収められると感じた――たとえ何も入っていなくても。
当初、これらの箱が何のためなのかははっきりとはわからなかった。しかし当時、彼はいつも耳を傾けていた貧しい人々との対話を続けており、彼らの苦しみを深い傷のように感じていた。それは祝福であり、あるいは末端でさえも血を流すような感覚だった。そこで彼は、捨てられた木材を丹念に釘で打ち合わせた、あの細長い奇妙な箱を全て蓄えることにした。いつかそれらが役立つ日が来ると確信していた。親友たちが他者から受けた不当な仕打ちへの報復として。
2024年2月23日 [13:50-15:30]
トリュフ』ロバート・フラー著
朝までに、幾つかの田舎の野生林市場の郊外にある希望に満ちた若樫の木々から、最高級の黒い冬の土壌に降り注ぐほこりっぽい冬の陽射しは消え去っていた。猟犬たちは静かに闇の柱へと駆け寄り、浅い穴へと潜り込む。彼らの無造作な掘り返しが獲物へと切り込んでいく。農夫たちは食料を採集し、黒い冬の樫の林で見つかった失われた盗まれた宝石の重要性の必要性を案じた。そこでは狭い道が、一貫性のない金色の月明かりの冬を育むだろう。
彼は狩り、20世紀の運命の転換が世界大戦を具現化する中をぶらつき、旅の不確実性へと戻る:田舎道、焼け焦げた大地、白亜質の土壌、闇の斑点へ、埋もれた薔薇へ。
薄暗い太陽の緑と白の日々、遠くに月光が輝く、辺縁の黄色い樫の木々に圧倒された壮観な空、田舎の狐のように軽やかに盗人を掘る犬たち、過去の朝の傷跡、儚く孤立した秘密と魔法と宗教と危険の墓の中で。神秘は、そのようなバレエの葡萄畑の発掘を促すかもしれない、厳粛さの問題、過ぎ去る確信の問題、眠そうな樫の木々の中を行進し、夜の彷徨い。
冥界の微妙な動き、影の商売;盗人への問い詰め:そうした犯罪物語こそが我々の盲目的な感性を映し出す、秘密の味わい、壮大な詐欺、売り渡された物語、より暗い幻想。
2024年2月24日 [22:01-23:55]
夜蛾』ロバート・フラー著
私たちは羊皮紙に書かれた判読不能な走り書きだった、君が燃える光へと飛んでいく私たちの音を聞くまでは。その前に私たちは、絹のように脆い淡い羽根を携え、太陽へと向かうイカロスのように、身近な光へとひらひらと飛んでいく姿を想像していた。紙の上のインクに過ぎなかった私たちは、敏捷な眼差しと指先、そして威厳ある楽器によって変容し、豪華な音の波へと転じ、絹のような私たちの心を満たすその過程に酔いしれていた。
かつて存在した私たちは、記号が歌と飛翔と鳥の悲しみへと変容するこの錬金術が、どうして可能だったのかと不思議に思っていた。私たちの翼はただ無意味に飛び回り、後悔もなく羽ばたくだけだった。それでも隣人たちは優雅に飛翔しながら嘆き、翼の哀切な響きが悲しげに太陽へと届いていた。
我々は再び塵となる運命にあった。それでも我々、あるいは我々、あるいはあなたが思う「我々」として、あるいは「我々」として、あるいは「あなた」として、我々を招く光の源、その源を探して飛び回っていた。しかし我々は紙の上の落書きに過ぎず、もし我々が存在したとしても、我々を我々たらしめたのはあなたの錬金術だったのだ。
夜蛾は道化師の派手な絹の衣装をまとう。知られざる夜明けが、闇に散る飛翔の中で彼らの人生に哀歌をもたらすのだ。そう、彼らは時に夢を見る。目を持たぬ眼が、船や波や生命の喧騒を見る夢を。そして振り返れば、彼らを見ぬ他の何ものかを見る夢を。なぜなら我々は幻影だったから。我々は存在した、しかし存在しなかった。それでも我々は飛んだ、風と歌の波を越えて。それらは儚い紙に走り書きされた存在に過ぎず、我々がそうであったように、やがて塵へと変わる運命だった。
我らは谷間にいた、夜、提灯のそばで。そして我らは、飛翔し、光となり、塵となり、鼓動する汝の心臓の平唱となった。それは永遠に鳴り響く鐘を招き寄せ、絶え間なく鳴り続ける鐘は永遠に歌い続けるのだ――谷間を、平原を、山を、海を。夜蛾の永遠に鳴り響く鐘を。我らはそれであり、永遠にそうあり続けるのだ。
2024年2月25日 [10:22-11:14]
太陽の舞手たち』ロバート・フラー著
蛍ではなく、太陽の蝿、舞う蝿。節足動物、有翅六脚類、自然の曲芸師、翼の相棒、スカイダイバー、太陽崇拝者たち。翼と風と太陽と歌を語り、魅惑的な美しさの動く幾何学模様、ホバークラフト、ハンググライダー、急降下爆撃機、野生の猫、ハリケーン、流れ星――すべてが語る、引力と斥力と無関心と自由落下と混沌の世界の物語。
光の中を、光として、光そのもののように動く様は催眠的だった。複眼と無限の敏捷性を備えた翼ある存在として、その短い生涯で数えきれないほどの日に、こうした軌跡を反復練習してきたかのようだった。高き太陽のきらめきの中で、星や彗星や小さな翼を持つ星系や銀河や宇宙の点として、果てしなく漂い続ける。決して同じパターンを繰り返さず、それらが発せられた源である宇宙そのもののように、この形からあの形へと絶えず変化し、一度たりとも繰り返すことなく、誰にも理解されることなど微塵もない。
彼らの舞いの意味とは?誰も問わなかった。それは彼らだけの自由な秘密であり、彼ら自身も気づいていなかったかもしれない。なぜなら彼らは踊っていたのだ、我々の狂気や日常の煩わしさから解放され、ただありのままに、何の気兼ねもなく、彼らなりの方法で交わり、誰かが理解しようがしまいが全く意に介さずに。それは渦だった、渦巻きだった、良き狂気の陶酔的な螺旋状の渦巻きだった。表層がどう見えようと心を温めるもの、彼らのように太陽の下で自由に踊るよう鼓舞するもの、彼らの善意の自由な螺旋に全身を浸されるものだった。
2024年2月26日 [21:33-22:11]
鏡』ロバート・フラー著
鏡に映る迷宮のような記憶をマクスに、そして当局に囁いた。当局の者たちは私に打ち明けた――少なくとも時折、自分たちがどうしてこれほど見過ごされてきたのかと疑問に思っていたのだと。今や我々がどう変容したか視覚化できる――道化師の落書きのようにギャラリー全体に映し出され、羽根の走り書きによって転化され、残るアブサンの味わいを経て、小麦畑を貫くガラスの門に映り、幻想の鐘の音として。後悔なき祝福に包まれつつも、出口なき音楽が響き始めた。周囲に映し出され、節くれだった蟬や花々の無限の比喩に溶け込み、その脆さの残響を永遠に歌い続ける。見知らぬ環境が生み出す聴覚体験の中で、光の中の哀しい足音が響く。
提灯近くの夜の葉、異なる翼と悲しみ、紙の上の墨のみ、塵となる運命が、サフランのほのかな香りと共に夜明けへ招いた。我々は絹のような闇であった、溶けた鳥たちの谷に隠された城、鐘の家、絶え間ない風について語っていたから――君はもう忘れた。君はたまたま呟きを耳にした、マンモスと哺乳類の物語を、それらを称賛しては、また無造作に夜の平唱の谷に散る飛翔の歌さえ聞かず;それはほとんど忘れ去られ、アイリスの野原の上の葉に覆われ、鮮やかな色で描かれた花々、太陽の音。
2024年2月27日 [13:32-15:21]
私のような人間』ロバート・フラー著
少なくとも私はそう思っていた——皆が私を好きだと。ところが噂話で、まったく逆の言葉を数多く耳にした。心配なら言っておくが、それで世界が崩れ落ちることはなかった。ほら、実はさ、人が俺をどう思ってるかなんて——ネタバレ注意!——全然気にしてないんだ。俺を好きなら、俺みたいな人間も好きになるのが当然だろ?でもね、ここには重大な問題がある:俺みたいな人間なんてどこにもいないんだ!君がまだ気づいてないかもしれないから、念のため言っておくよ。
さて、肝心な話に入ろう。この連中が突然、仲介のエージェントも通さず直接私に連絡してきたんだ。「君の伝記映画を作りたい」ってな。マジで失禁しそうになったぜ!知ってるだろうが、俺は典型的な無名野郎だ。そんな俺を、誰が誰だか全く知らないまま、大物プロデューサー連中が顔も見ずに仕事をオファーするなんて、まったくもって荒唐無稽この上ない話だった!すぐにエージェントに電話で確認したら、彼女も全く知らないと言う。そして何度も「気をつけろ、多分詐欺だ、デマだ、誰かがからかってるだけだ、腹を抱えて笑ってるだけだ」と忠告を繰り返した。
言うまでもないが、俺自身も怪しい匂いを感じた。何かおかしい、良い意味じゃない。だから俺は完全に無視した。
その件はそのまま放置し、あまり気に留めていなかった。ところが一週間後、同じ男から緊急事態を告げるようなコードブルー級のメッセージが届いた。今すぐ話さねばならないと主張する内容だ。
そこで私は落ち着いて(そういう場面ではこれが私の得意技だ)、男に返信した。「笑、おい、どうした!?」 待っても待っても返事は来ず、そろそろ寝る時間になった頃、ようやく奴から連絡が来た。でも電話だった。俺はちょうど下着姿になって、孤独な枕との熱いデート前に熱いお風呂を沸かそうとしてたところだった。ちなみに知ってるか知らんかわかんねえが、俺の枕はめっちゃ嫉妬深いんだぜ。だから深呼吸して、ズボンをまた履き直して、電話が鳴りっぱなしになるまで放置して、やっと出たんだ。
そいつはすぐに本題に入った。一言も遠回しにせず、ストレートに切り込んだ。「ダルトン様」——俺は即座に遮った。「モートだ。犬までがモートって呼ぶんだぜ」 —「モートさん」——この呼び名は流しておいた。話をどこまで進めるか確かめるためだ——「貴方はこの由緒ある業界では無名ですが、それこそが我々が求めている人物像にぴったりです」気まずいほどの長い沈黙が流れた…正直、腹が立つべきか、ようやく誰かに認められたことに心底喜ぶべきか、判断がつかなかった。つまり、誰にも知られてないからって、ようやく俺の哀れな存在に気づいたって、それって褒め言葉なのかよ!?
深呼吸して選択肢を考え、結局はあの真夜中にバー・シニスターで夜食と真剣な話し合いをすることに合意したんだ。ウォーク・オブ・フェイムのすぐそばにある店だ!間違いなく、これでやる気が湧いてきたぜ!
さて、俺は最高の服を着込み、数本の乱れた髪さえも整え、一番のオックスフォード靴を磨き上げ、自信満々で出かけた。この出会いが、今まで見過ごされてきた一生に一度のチャンスに変わることを確信していた。
私は時間より少し早く、15分ほど前に到着し、バーの特等席を何とか確保した。相手——ダグ・ダーネルという男——は夜の真夜中ぴったりに現れた。彼は親切にも、誰にも盗み聞きされずに率直に話せるよう、個室を確保しようと提案した。私は承諾した。
個室に着くと、彼は食事も飲み物も注文する前に(私の考えではダーネルが奢るはずだったのだが)、すぐに本題に入った。「モートさん」——その呼び名に私は動揺したが、言葉を飲み込んだ——「モートさん、私たちは少なくとも20年以上にわたり、あなたの長く輝かしいキャリアを追ってきました」——その言葉に私が二度見したのを彼は気づいたに違いない、あまりにも露骨だった——「そしてナックスター・エンタープライズ」——そんな会社、初めて聞いた!——「は、最新のテレビシリーズにあなたを起用することを決定しました」
平静を装おうとしたが、さっき食べた昼食が込み上げてきて、できるだけ控えめに尋ねた。「へえ、そうなんですか!タイトルは?」すると彼は静かに、自信に満ちた、かすれたようなささやき声で告げた。「『ノーバディーズ・ビジネス』」その瞬間、私は激しい咳込みに襲われ、ダグ氏に「まず強い酒を注文してくれ。それから君の提案を詳しく話し合おう」と言った。
というわけで、奴はダーティーマティーニを2杯注文した——正直言って俺の第一選択じゃないが 正直言ってね——それが運ばれてきて、二人で一口ずつ飲んだところで、彼は本題に入った。ある種の連中が、自分たちにとっては神の意志だと思っていることを実行する時によくやる、綱渡りのようなことを試み始めたんだ。つまり、ほとんど何も話さないのに、同時に相手に自分の商品や、相手にやってほしいことに夢中にさせるというやつだ。
おい、ダグさんよ——彼はことわざのチューリップの周りをそっと歩き、私の頭の中に浮かぶ核心的な疑問を巧みに回避する。つまりだ:「ノーバディーズ・ビジネス」って一体何なんだ!?だから俺は彼に少しぐずぐずさせてやった——知ったかぶりしてね。彼はあれこれ話すが、肝心なことは何も言わない。ついに俺はタイムアウトの合図を送り、「ストップ!」と叫んだ。
彼は私を睨みつける――ほんの少しだけ――そして柔らかい口調で言った。「聞いてください、モートさん。ナックスターは、君を非常に成功するシリーズに起用すること、そしてそれが君に永続的な名声と数えきれないほどの機会をもたらすことを、真剣に考えているんです。ただ、ここにサインしていただくだけです」
まったく腹が立つ!俺ははっきり言った。「何にサインしてるかもわかんねえんだ!はっきり言えよ、この番組の正体をな!」
奴は汚れたマティーニの最後の一口をむせびながら飲み干し、すぐに追加を注文すると、給仕が席を立つより早く、馬のケツみたいな口調で話し始めた。そう、お察しの通りだ!『ノーバディーズ・ビジネス』だ!まるで奴が、社会学の論文か何かで夢にまで見たのに書き忘れた断片を、ぶつぶつと暗唱してるみたいだった!
「フォーカスグループ調査の結果、貴殿のような才能ある人物こそ、我々の新テレビシリーズで主役に据えるにふさわしいと判明しました。このジャンルを扱う主要批評家の見解においても、間違いなく最高峰の評価を得られるでしょう」
おいおい!今マジで何か言ったのか!?マジで失禁しそうだったぜ。
だから本題に入った。「ダグさん、このご高名なプロジェクトに熱意を燃やされているのは存じ上げております。きっと眠れない夜を何度も過ごされたことでしょう。しかし」——わざと大きく喉を鳴らして——「一つ聞きたい。なぜ私のような無名の人間を、他の誰でもない、他のどんな無名の人間でもなく、選んだのですか?」ちょうどその時、待望の新鮮な飲み物が届いた。ダグ氏は恥ずかしそうに数口含み、咳払いをしてから答えた。
しかし彼が口を開く前に、私は切り込んだ。「その答えの前に、この新たな役柄の要件を満たすために、私に何が必要ですか?」 彼は言った。「大したことじゃない。台本を読んで、君らしくいればいい。それ以外に特にやることはなく、我々が面倒を見る」そこで私は羊皮紙に書かれた、ほとんど判読不能な走り書きをざっと目を通した——私は速読の達人で、そんな幼稚な駄文でも問題ない——そして一つだけ目立った点があった: あのクソ脚本の中の役柄は、一つ残らず同じクソみたいな役名で統一されていたんだ:ミスター・モート!
だから俺は最高の半笑いを浮かべて、そっと奴に尋ねた。「で、どうするつもりだ?俺をクローンするつもりか!?それともまたあの新しもの好きのAIクソみたいなものか!?」正直言って、かなり腹が立っていたんだ。すると奴は、俺が署名するはずだった書類の細かい文字を指さした。
「ここに明記されてますよ」——彼は激しく指さし、わざとらしい身振りで——「ここには、あなた自身が——スタントダブルでも、クローンでも、AIの戯言でもなく——あなた!あなただけが、この尊い脚本の全ての役を演じるべきだと。エキストラ役すらも!」奴は文字通り台本を投げつけてきたが、俺はかわした。
どうやらこれで、お互いの認識がほぼ一致したようだ。私が落ち着きを取り戻すと、口を開く前に彼が言った。「君みたいな人間は他にいない!」
私は面目を失いながら署名欄にサインをしながら、主に自分自身と、聞いてくれる誰かに囁いた。「そして、私を好きになる人間もいない」
2024年2月28日 [18:14-20:27]
聖書』ロバート・フラー著
牧師は地獄の炎のような目で私を睨んだ。毎週日曜日のことだ。いつもの席に座り、参列者のボンネットを眺めていると、必ず胸のあたりに冷たいしびれを感じた。彼が狙うその場所、礼拝の決まった時間帯に。大抵は第二賛美歌と第三賛美歌の間、陳腐で過剰な説教中に居眠りしていた会衆の半数がようやく惺慄から覚め始める頃だった。
ご存知の通り、彼はそれほど感銘深い説教者ではなかった。中学生ですら絶対に犯さないような文法ミスを、私は常に見抜いていた。私の見解では、彼は魂を救うためにも文章が書けなかったのだ。
それでも彼は聖書を引用するのがお決まりで、まるでそれがすぐに廃れるかのように。「人を裁くな、裁かれないためだ」。冗談じゃない!あの鋼のような眼差しが私の肉を焼き尽くす時、一体どんなことが起こっていると思う?間違いなく、彼の視線だけで永遠の地獄に堕とされた時、私の考えではキリスト教徒として取るべき唯一の行動は、お返しをすることだった。そう、私は喜んで罪を告白します、神父様。あの埃まみれの書物に書いてある通り、邪眼には邪眼で応える。それが俺の信条だ。
お前ら、神聖な心ゆくまで俺を嘲り、拒絶しても構わない。だが、俺の言葉の重要性と意味は、ほんの少しも変わらない。俺が知っていること、俺が見ていることは、それだけの話だ。
だが説教は、あの地獄の賛美歌の拷問室も三分の二ほど進んだところで、突然方向転換する。そしてほら! あの不機嫌な小僧のグリンチが、史上最悪のニヤニヤ笑いの代名詞へと変貌するのだ。
これはいつも、いつも、若造だった頃の俺を思い出す: あのくそったれな賛美歌集がずっと気になってたんだ。13番と666番の賛美歌って、一体何を歌うんだ? 特に後者は数字的に発音不可能だろ? ヘクサコシオイヘクセコンタヘクサフォビア。解読してみろよ…もし勇気があるならな。
だから俺は、どんな進取の気性を持つ小僧でもやることを実行した。あの番号に自分で歌詞を付けたんだ。トラブルを避けるため、親がかなり信心深い自負を持っていたから、部屋でこっそり歌うようにして、絶対に大声で歌わなかった。
でもはっきり言っておくが、後になって、俺の輝かしいキャリアの中で、あの無駄遣いした青春時代の歌詞を、数多くのデスメタルの宴で再利用したんだ。自分がガタガタ歌ってる言葉が誰にも理解されないって、十分承知の上でな。幸いにも両親は現れなかった。
いずれにせよ、プレッチが少し落ち着くと、彼は特に女性に対しては、あふれんばかりの熱意と陽気さを見せた。まるで踊っているように見せかけるのに必死で、両足が左足のように不器用なせいで、つまずきそうになりながら、一人ひとりの女性と踊ろうとした。その様子は吐き気を催すほどだった。
だがあの演技は、閉会の祈りの後に始まったものだ。いつも同じ使い回しのクソみたいな祈りで、彼は全能の神様の前で究極の服従とへつらいを強調する。正直言って、神様なんてそんな戯言に全く興味ないだろうに。彼は「これを祝福し、あれを祝福し」と、まるで自分が全能者をこき使っているかのように、タタタタタと連発した。はっきり言っておくが、本物の祈り――神と心を通わせる真剣な祈り――には何の異論もない。だが見せかけの偽善や茶番には、本当に薄皮一枚の我慢強さで、一切の寛容も示さない。
だから、いつも全部終わった後はコーヒー交流会があって、みんなが気分を良くするために、同じ罪人同士で交流するんだ。効果はゼロだけど、せめて気分は盛り上がる。
すると説教師が聖なる御姿を現してご機嫌取りに来る。何とか避けようとするんだけど、彼がスイーツのトレイを持ってるから、我慢できずに手を出してしまうんだ。私は数個の特選菓子を掴み、閣下の目にはあまり貪欲に見えないよう努めたが、彼の思考は、神に感謝、あちこち飛んでいて、お菓子トレイには向いていなかった。しかし、その戦利品を抱えてこっそり逃げ出そうとした時、彼は突然魅力の弾丸を発射し、音楽監督をやりたくないかと尋ねてきた。どうやら彼はまだ私の賛美歌集を読んでいないようだ。
2024年2月29日 [21:21-22:32]
レシピ』ロバート・フラー著
ある日、ふと「相手の食習慣を知るのは面白いかもしれない」という考えが浮かんだ。
その日、私は美食家になったのだが、どうか早合点しないでほしい。
私の調査——何と呼ぼうと、博士課程で所属していた部署から正式に認可されたものだ——は単純な前提に基づいていた:人の食を知ることで、その人自身を知ることができる。
そして彼らの食生活は、控えめに言っても実に興味深い。我々凡人には到底近づけぬあらゆる種類の食物を口にする。それなのに、彼らはあらゆる豪華な料理を堪能しながらも、その糞は誰よりもひどく臭うのだ。
とはいえ、私の好奇心は抑えきれず、行った実験は「他者がどう食べるか」を知るためというより、単にこれだった:他者が体内に取り込み吸収するもので真にその人物を知ること——そしておそらくそれによって、彼らのような存在になること。
そこでまず、適切な被験者を探す必要があった。親族?親友?いや、それらは近すぎて危険だ。学位取得の規定と指導教官の要求に従い、比較的匿名の被験者、少なくとも私と直接的な繋がりのない人物を見つけることが必要だった。
そこで私は高級料理における大食いの研究に没頭し始めた。その資金の一部は、匿名を条件とした複数のクラウドファンディングからの寛大な寄付によって賄われた。
こうして毎週火曜日頃、私は新しいレストランを訪れ、メニューで最も高価な品々を試食した。しかしそれでも研究プロジェクトには役立たず、ただウエストラインに余計な肉をつけただけだった。とはいえ、その喜びは私だけのものだったと認めざるを得ない。
論文プロジェクト開始から半年後、指導教官が緊急会議を招集した。当然ながら私は事情を気にかけた。何しろ研究資料と膨大なノートは全て提出済みだったのだ。そこで彼らは率直に言い放った。この研究プロジェクトにおいて、私は独自のレシピ集を著した適切な対象者を見つけ出し、自らそのレシピを調理し、摂取した上で、摂取後の身体的・精神的状態を報告する義務を負うことになったのだ。
彼らの指摘は確かに的を射ていた。私はすぐにその正当性を認めた。
こうして私は「他者になる」という世界へと足を踏み入れたのである。
この学術分野を取り巻く謎は、一般大衆にはまだ十分に知られていない。この分野の科学的側面は、いわゆる適切な「ピアレビュー」の欠如によって未だ阻害されている。だから私の指導教官たち、あえて言えば師匠たちは、私の直感に反してさえ、この全く新しい研究領域へと私を押し進めていたのだ。
そして、以前の誤った努力で増えた体重を落とした後、本格的に研究を始めた私は気づいた。新たな栄養補給のたびに、私の表情は明らかに変わり、全体的な態度はより優雅になり、何よりも自分の要求を主張するようになり、スーツはよりシャープで芸術的に仕立てられるようになったのだ。そして身長が数インチ伸びた——少なくとも周囲はそう言っていた。
研究の主軸であったレシピ群は、運悪く後世に伝わることはなかった。指導教官たちは後に指摘した——委員会メンバーの誰一人として、それらのレシピを検証できなかったと。
そこで私は料理対決を決行した。これが私の学術的キャリアを永遠に立証するか、葬り去るかの分かれ目となる。招待者は委員会全員——表向きは私の運命を決定する者たちだ。
彼ら全員への挑戦状は単純明快だった:ここにレシピがある。各自の技量を尽くして完成させよ。その結果を存分に味わい、何が起きるか見届けよ。それだけだ!
誰もこの挑戦に応えられなかった。
私は特別な情報源から授かったレシピで調理した豪華な料理を、ひたすら食べ続けた。そして年月を経て、私は自らを大いに楽しみながら、その情報源そのものとなった。
2024年3月1日 [20:12-21:09]
ノース・リバティ』ロバート・フラー著
沿岸部の人間は寒さなんて知らないんだ。東海岸で華氏0度(摂氏約-18度)まで下がったり、西海岸で30~40度(摂氏約-1~4度)や50度(摂氏約0~10度)まで下がると文句を言うけど、本当の寒さなんて知らない!本当の寒さとは華氏30度(摂氏約-34度)以下のことだ——風冷効果を考慮すれば摂氏約-70度だ。まず車のエンジンをかける時は、命がけで神に祈るんだ。明日がないかのように。そしてダウンタウンに着くと、グレート・ミッドウェスタン・アイスクリーム社からデッドウッド・タバーンまで、たった5分の道のりを歩くだけで命の危険を感じる。プラリー・ライツの真向かいだ。そう、その短い道のりで凍傷になるかもしれない!
だがこの話はそれではない。
むしろ暖かな昼と夜の話だ。マグガード通りの地下アパートから、数メートル先を走る貨物列車の金属が軋む歓喜のような音を横目に、ドアや窓越しに、あるいは庭でくつろぎながら、無数の蛍が狂ったように光る光のショーを見ることができた。
時にはそうした昼も夜も蒸し暑く、時にはうだるほど暑かったが、それほど気にはならなかった。なぜなら素晴らしい仲間がいたからだ。ロバートの素晴らしい屋根裏部屋で、カシオの電子楽器を駆使した即興演奏に興じることもあれば、ケネスが学外に構えた書斎のような住まいで、ロバートを含む彼の教え子たちと共に過ごすこともあった。名目上は音楽について話しているように見えても、実際には批判的思考の技法など、同様に重要な多くの事柄について語り合っていたのだ。そしてケネスが「スローアップ」と呼んだ行為を実践することもあった。表向きは音楽について話していたが、批判的思考の技法など、同様に重要な多くの事柄についても語り合った。そしてケネスが「スローアップ」と呼ぶ行為も行った。
このグループにおける学びは、単に登録したプログラムだけにとどまらなかった。音楽学部の学位取得を目指す学生たちは当然ながら音楽そのものを学んでいたが、教師たちのおかげで、その過程で遥かに多くのことを吸収していたのだ。
そしてあの特別な場所があった。二つの部屋で構成され、広い方にはムーグ・シンセサイザーと昔ながらのオープンリール式録音機材、さらに当時テープを切り刻み斬新な方法でつなぎ合わせるのに使われた装置が置かれていた。現代のように全てをデジタルで処理できる時代や、自らの努力や創造性の一片も介さずAIコンパニオンに「音楽」を作らせられる状況とは比べ物にならないほど複雑で奥深い作業だった。角を曲がった小さな部屋には小型シンセサイザーが置かれていたが、それ以上に重要なのは、単にUSと呼ばれるプログラムを用いて独自のコンピュータ音楽を創作する拠点となっていたことだ。
二つの部屋は総称して電子音楽スタジオと呼ばれていた。
このスタジオの最も特筆すべき点は、参加するために音楽学部の学生である必要がなかったことだ。なんと画期的な概念だろう!創造性の民主化!恣意的な門番を排除する!そして私たちスタジオの者たちは、階下の連中をさほど高くは評価していなかった。彼らは終身在職権を狙ったり、自称の栄光に安住したりしながら、音楽研究の本質についての彼らの過度に制限的な考え方に賛同しない私たちに対して、陰険な報復を続けていたのだから。彼らは自分たちが考える「音楽あるべき姿」への、比較的退屈な試みを創作していた。一方、スタジオの上階にいる私たちは常に、そうした「音楽のあり方」という概念そのものに疑問を投げかけていた。
イアノスが披露してくれた、あの忘れられない発表会があった。スタジオの参加者たちが、ムーグやその他の機材を使って創作した作品を発表する機会は頻繁にあった。イアノスは物理学の学生で、私の知る限り音楽のレッスンを受けたことは一度もなかった。それでもスタジオの機材で彼が作り出したものは恍惚的で、魅惑的で、私がこれまで聞いたことのないものだった。
しかし、蛍やその他の夏の夜の営み、自然が惜しみなく与えてくれる光景や音に戻ろう。
ある時、キャンパスから北へ約8キロ離れた場所で開かれたパーティーに招待された。親友のアンとマイケルが誘ってくれたのだ。記憶では、そこは素晴らしい土地で、当時私にはほぼ大邸宅のように見えたかなり大きな家——田園地帯に広がる素敵な邸宅——だった。到着した時にはすでにかなり暗くなっていた。私たちは皆、いつものように騒ぎに興じていた。あれこれおしゃべりに花を咲かせ、用意された様々な飲み物を次々に味わっていた。
そんな中、私は一瞬外へ出た。それは永遠とは言わないまでも、長く感じられる瞬間となった。外には他の人たちもいて、食べたり飲んだり、楽しげに騒いでいた。もちろん、流れている音楽に負けないほどの大声で話していた者もいた。しかし私はただ、影の中で奏でられている交響曲に耳を澄ませていた。美しく官能的な音の渦が、私を完全に捉えていたのだ。
これこそが、教授たちが教えてくれたものだった。しかし誰も耳を傾けなかった。
2024年3月2日 [15:39-17:03]
ホットワイン』ロバート・フラー著
暖炉の周りではいつも、赤ワインにするかポートワインにするか、タウニーポートにするか、あるいはワインとポートのブレンドにするかについて、熱い議論が交わされていた。決着がつくことは決してなかった。少なくとも、そこにいた誰もが納得する形では。集まった者の中には、この時期は遅すぎると、祝祭シーズンはとっくに過ぎ去ったと不平を漏らす者もいた。しかし最初の batch が皆に振る舞われると、そんな呟きはたちまち消え去った。
いつもどこかの秘密の隅に潜んでいる猫でさえ、この熱くて香辛料の効いた発酵赤ぶどうの飲み物を祝うのにふさわしい時が、まさに今この瞬間だと同意した。外では雨か雪か、その中間のような天候で、心を温める何かが必要なほど寒かった。猫はそれをよく知っていた。温かな球体に丸くなり、そのほっこりとした不思議さを存分に味わうたびに。
私たちはキッチン当番を交代し、スパイスワインとその近縁であるポートワインについて、可能な限り多様な解釈を引き出した。それがスパイスワインの本質を理解する鍵だったのだ。中にはミニマリストもいて、シナモンとクローブのみ、それも棒状のものだけを使うべきだと主張する者もいた。辛口か甘口か、通常醸造か遅摘みか、強化ワイン(ポートのように)にするか否か——意見は分かれた。どの品種が最高のスパイスワインを生むか、あるいは特定の赤ワインブレンドが特別な輝きを加えるかという深い議論さえ交わされた。
そしてもちろん、豪華なチーズ盛り合わせが常に用意されていた。入手可能な最も珍しい逸品ばかりを厳選したものだ。通常はシャープチェダーが1~2種類、フレンチオニオンやワイルドモレル&リークジャック、クランベリーなどのフルーツを練り込んだソフトタイプの山羊乳または羊乳チーズ、そしてほぼ必ず素晴らしいブルーチーズが揃っていました。誰かが必ずたっぷりのバゲットを持ってくるので、スパイスワインは素晴らしい宴と良き仲間との集いの口実に過ぎなかったのです。
会話は時に仕事の話に及ぶこともあり、 技術者、作家、食通、芸術家、その他多くのクリエイティブな人々が祝宴に加わっていた。夜のモルドワイン(ポートワインベース)の影響もあって、人々は様々なショートブレッドやクッキー、特にダークチョコレートやトリュフ(常に人気だった)といったお菓子を持ち寄った。そしてモルドワインとお菓子が人々の緊張をほぐすと、即興の音楽や演劇、ダンスが始まり、 視覚芸術家たちは脇に座り、スケッチブックが埋まるまで、あるいは鉛筆やパステルが芯まですり減るまで描き続け、必ず1人か2人の映像作家が技術を磨いていた。時折誰かが、最初は誰も理解できないほど無表情で面白いジョークを飛ばしたり、ひどくつまらない駄洒落を口にしたりすると、大抵は困惑した溜息が場を包んだ。
するとまるで合図でもあったかのように、猫がふらりと現れ、全身を最大限に伸ばすと、暖炉のすぐそばにどっかりと腰を下ろす。そして可能な限り誇らしげに身繕いを始めるのだ。そのたびに、何が起きていようと、部屋中の全員が動きを止め、猫をじっと見つめる。猫はそれを承知していた。
2024年3月3日 [19:15-20:00]
時計』ロバート・フラー著
つい最近のことだ。私は何の疑いもなく眠りについた。真夜中の鐘が鳴った後に何が起こるかなど知らずに。まさにその時、最初のチクタク音が響いた。時計塔の周りを旋回するカラスたちの夢の中、城や大聖堂や要塞の夢の中、チクタク音は増え続け、それぞれが独自の時計を持っていた。それぞれの時計が狂ったように渦巻くのが見え、それらは復讐心すら感じさせる勢いで増え始めた。
最初は城の奥深く、地下牢のような場所にいた。そこには痩せた野良猫がうろつき、大きなネズミが必死に逃げ惑い、視界の限り広がっていた。そしてもちろん、狂ったように渦巻く時計の群れが毎秒増え続け、ますます執拗に時を刻んでいた。私が彷徨った通路は、明らかな機能を持たない歯車で埋め尽くされ、ただ騒々しく唸り続けていた。
そこには無造作に置かれたチェスの駒があった。より強力な駒——クイーンやルーク、そして非常に脆弱そうなキングさえも——だが、どれもチェス盤には固定されていなかった。それらは見えない力に動かされ、たださまよっている。奇妙なことに、それらのぎこちない動きの一つ一つには、ランダムに黒と白が交互に現れる四角い影が伴っていた。駒が現実のマスから仮想のマスへぐらつくたびに、猫たちは鳴き声をあげ、威嚇し、唸った。なぜなら、その不自然な動きが毎回ネズミを追い払うからだ。時計は毎秒増え続けていた。
すると突然、私は尖塔の時計の周りに群がるカラスたちに囲まれた。時計は依然として真夜中のまま止まっていた。どうやって空中に浮かんでいるのか全くわからなかったが、絶えず自由落下している感覚が続き、下の岩や堀に激突しそうだった。時計の群れが刻む新たな刻ごとに、私の不安は増幅していった。それらはますます私を追い詰め、次第に乱れ始め、不協和音を増幅させていた。
そして私は、旋風か、カラスの背か、あるいはカラスの渦巻く漏斗雲に、一気に連れ去られた。カアッという鳴き声が狂乱の坩堝と化し、無数のカラスの群れが無限の渦、横向きの八の字を描きながら大聖堂の双塔を囲んだ。十二使徒像とバラ窓の近くで、耳を澄ませばあらゆる竪笛の音色、羽ばたきや羽づくろいのかすかな音さえ聞こえた。
すると突然、カラスの鳴き声が途切れた――まるで時計がいつもそうするように、今もなお私の疲れ果てた頭の中で必死に刻み続け、刻みごとにますます痙攣的に――そして私は死の深淵へと、魂を救うために下級聖職者の一人によって祝福されている開かれた墓へと、ひたすら落下していくのを感じた。聞こえるのは嘆きと甲高い笑い声だけだった。すべてが死体のような不気味な動きと、罪の渦巻く影に包まれていた。
墓が開かれると、無数の虫が這い回り、モグラやハタネズミ、トガリネズミの掘った穴は四倍に増えた。町中心部の住民同様、彼らも儀式に怯えていたのだ。白と黒の四角い影が時折姿を現す。ほとんどの場合、チェスの駒は付いておらず、たまに紫と白の派手なチェッカー模様の衣装をまとった司教が、恥ずかしそうに威厳を装うこともあったが、突然、不可解にも、慌てて再び隠れ場所へ飛び込んでいく。
時計が私への攻撃を続け、混乱した頭蓋骨に残っていたわずかな正気さえ貪欲に食い尽くしていく中、私は無名のトンネルへと暗い誘引を感じた。おそらく自ら掘ったわけではない大きなハタネズミが、そのトンネルを堂々と利用していたのだ。トンネルは彼よりはるかに大きかったが、目の前にあるものを遠慮なく使うことに何の躊躇いもなかった。彼には何か謎めいた使命が課されていたのかもしれないが、私は問い詰めなかった。ただ盲目的に従い、棺や石棺、散乱するミイラ化した遺骸を通り過ぎ、この通路がどこへ続くのかと好奇に駆られた。通路の薄暗い奥から抜け出し、赤・白・緑の斑模様の三色で縁取られた不揃いな階段を登り終える頃には、そのハタネズミの姿は消えていた。
かつて狡猾な囚人を拘束した金属の足枷や牢獄の鉄格子を通り過ぎると、様々なネズミや害虫、時には迷い込んだハムスターまでもが、まるで誰にも構われないかのように走り回っていた。特に野良猫が軽食を求めて室内へ踏み込む時は、その様子が顕著だった。そして、カビの生えた凸凹マットレスの残骸の中では、トコジラミやゴキブリが這いずり回り、あちこちへ飛び跳ねているのを目撃した。時折、銀魚がヌルヌルと流れ、神のみぞ知る場所へ急いで消えていくこともあった。時計はまったくもって不気味になりつつあった。ライオンの群れを貪り食うジェットエンジンの轟音へと膨れ上がり、その不規則なリズムに心臓が耐えられるか、何が起こるか不安になった。何匹かのトコジラミは、一言も発せずに魔法のようにポーンへと変貌したが、それでも影のマスから影のマスへと必死に駆け回り続けた。白と黒が激しく混ざり合い、灰色の渦となっていた。時折、時計のどれかがポーンを軽食にする。それが私の身に対する彼らの飽くなき攻撃を助長するだけだと知ると、私は心底苛立った。ナイトは白から黒へ、黒から白へと跳び回り、その間のマスを飛び越えていた。
ついに息継ぎのために地上へ出ると、騒がしいカラスが群がる監視塔へとたどり着いた。よろめき、よろめき、正気を急速に失いながら、狂ったように咲き乱れる庭園を通り過ぎると、灰色の歩兵たちは「死体安置所」と記された灰色の建物へまっすぐ導いた。そしてそこで、ついに最後の敵を見つけたのだ。
2024年2月27日 [19:14-19:24];2024年2月29日 [11:44-14:38]